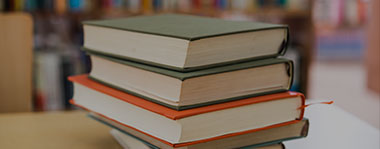マーケティングのジレンマ・・・No.91 平均は格差を隠す
コラム
リンクトイン
 https://www.linkedin.com/pulse/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%9Eno91-%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AF%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E3%82%92%E9%9A%A0%E3%81%99-mitsuo-sakai-%E9%85%92%E4%BA%95%E5%85%89%E9%9B%84-gzr5c/?trackingId=YlYW7O%2FgLywRJ4cKua%2Bdqw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%9Eno91-%E5%B9%B3%E5%9D%87%E3%81%AF%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E3%82%92%E9%9A%A0%E3%81%99-mitsuo-sakai-%E9%85%92%E4%BA%95%E5%85%89%E9%9B%84-gzr5c/?trackingId=YlYW7O%2FgLywRJ4cKua%2Bdqw%3D%3D

あなたは現在どれだけ貯金があるでしょうか? ちなみに高齢世帯の平均貯蓄額が1,625万円と知ったら、驚きませんか?実はここに平均値の盲点があります。
定量調査では平均値でなく、中央値で判断する
定量調査で気をつける点は、平均値で判断することです。その典型例が貯蓄額の平均値です。2022年厚労省の『国民生活基礎調査』を例にすると、世帯主が65歳以上の高齢世帯の平均貯蓄額は1,625万円となっています。こんなに多額の貯金を多くの高齢者がしているのかと思うはずですが、ここに盲点があります。
最も金額が多いのは貯蓄3000万円以上の世帯(全体の16.5%)ですが、この階層には、5000万円とか1億円、さらには10億円というような超富裕層も含まれています。報告書に出ている平均値(1,625万円)は、こうした人たちの数字によって吊り上げられているわけです。
実際のデータでは貯蓄がゼロという分布も12.9%存在しますから、こんなに多いはずはないのです。
こんな場合は、中央値を参考にすればよいと、社会教育学者の米田敏彦さんが指摘しています。前述した2022年の『国民生活基礎調査』のデータから、高齢世帯の貯蓄額の中央値(累積%値=50)を計算すると700万円になり、平均値の半分にも達していません。平均値と中央値がかけはなれているのは、それだけ格差が大きくなっているわけです。実態を把握する際には、平均値だけでなく、中央値を見ることが重要なことがわかります。