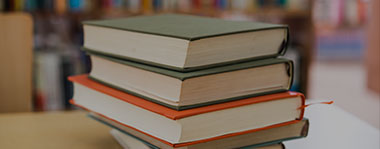価値のジレンマ・・・No.74 アメリカから見えてくる先進国が共通して抱える問題

アメリカでは、中間層になるのも困難な社会状況になっているという指摘があります。なぜ、そして何が、こうした事態を引き起こしたのでしょうか。アメリカが抱えるこの問題は、実は日本にも共通点があるようです。
パンデミックとその影響によるインフレで、アメリカでは約3,800万人(およそ9人に1人)が生活必需品すら不足する貧困状態にある
ウォール・ストリート・ジャーナルなどが2024年7月に実施した調査によると、「持ち家」「金銭的安定」「快適な老後を容易に手に入れられる」と回答したアメリカ人はそれぞれ約1割しか存在しませんでした。
パンデミックとその影響によって激しいインフレに見舞われ、アメリカでは約3,800万人(およそ9人に1人)が、生活必需品すら不足する貧困状態にあると社会学者のマシュー・デズモンド氏が分析しています。所得の格差を示すジニ係数は2023年に0.485となり、騒乱発生リスクがあるとされる水準0.4を上回っています。
アメリカ社会がこのような事態になるきっかけは、2008年に引き起こされたリーマンショックです。当時の住宅の値下がりによる損失は5.5兆ドル(当時の為替レートで約570兆円)、住宅の差し押さえは400万件を超え、2009年までの2年間で延べ5,280万人が一時解雇(レイオフ)の対象となり、約860万人が職を失いました。住宅相場の下落とローンの焦げ付きが金融危機と景気後退を引き起こし、多くのアメリカ人の生活が破綻しました。経済的に豊かではない層は住宅購入時にローンに依存する割合が高いため、住宅価格の値下がりにより多くの人たちが債務超過に陥りました。
こうした事態を受けてアメリカ政府は金融システムの安定を最優先し、住宅ローン負担の軽減などを行いましたが効果は十分ではありませんした。
その後、製造業の雇用はコスト競争力で勝る新興国へシフトしていき、この流れは金融危機の収束後も止まらず、アメリカの製造業の雇用者数は現在でも危機前の水準を約80万人下回っています。IT企業などでケタ違いの高給を得られる限られた層がいる一方、多くの一般労働者は低賃金のサービス業などの職に甘んじています。並行してグローバル化する資本主義の力が拡大していき、新興国の余剰マネーが流れ込み、アメリカの住宅バブルは拡大していきまた。
積み重なった16年の間に、アメリカの中間層が立ち直ることはできませんでした。現在の大統領選で「中間層の再興」を両陣営が訴えているのは、ここに背景となる問題があるわけです。
関税の引き上げや補助金で国内産業を守ろうとすると、長期的視野に立つとアメリカの国際競争力は衰え、雇用にも悪影響が出る恐れもあり、問題の解決は容易ではありません。
グローバル資本主義にどう立ち向かうかという難題は、日本を含む先進国全体に共通している問題でもあるのです。
参照:日本経済新聞社「疲弊する米庶民、金融危機の傷今も 次期大統領に難題 日経新聞 米州総局長 山下茂行氏」記事