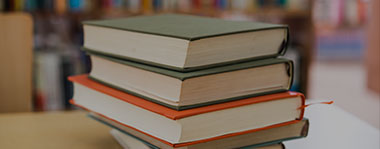価値のジレンマ・・・No.89 上司がAIになる日は来るのか!?

既にAIを導入した企業では、AIが24時間稼働し、感情やバイアスに左右されずに意思決定をしています。スケジューリング、在庫管理、戦略判断の初期段階など、効率化や精度向上が求められる分野では、人間を超える成果を見せつつあります。では今後AIが私たちの上司になる時代は来るのでしょうか?
膨大なデータをもとに24時間稼働し、感情やバイアスに左右されずに意思決定するAI
実際にAI上司のもとで働いた社員からは、疎外感やチームの士気低下といった声もある
いま、AIが企業のリーダーとして実際に任命され始めています。
ポーランドでラムを始めとするスピリッツなどのアルコールを手掛けるDictador社では、AIロボット「MIKA」がCEOに就任。中国のゲームなどのテクノロジー企業のNetDragon Websoft(ネットドラゴン・ウェブソフト)は、子会社Fujian(福建)NetDragon Websoftの「※輪番CEO」に起用。英国の知識共有プラットフォームのDeepKnowledgeでは、AI「Vital」が運営マネージャーとしてタスクの割り当てやプロジェクト進捗の監視や設定された指標に基づく従業員評価などを担うなど、AIが“経営の現場”に入り込む事例が次々と登場しています。
こうした取り組みに共通しているのは、AIが膨大なデータをもとに、24時間稼働し、感情やバイアスに左右されずに意思決定をしている点です。スケジューリング、在庫管理、戦略判断の初期段階など、効率化や精度向上が求められる分野では、人間を超える成果を見せ始めています。
しかしすべての経営判断を、AIに任せられるわけではありません。社員との信頼構築、創造性の喚起、組織内の微妙な力学を読み取る「感情的知性(EI:エモーショナル・インテリジェンス)」の領域は、現状のAIでは対応が難しいままです。実際にAI上司のもとで働いた社員からは、疎外感やチームの士気低下といった声が報告されています。
2024年のAonの調査では、AI導入企業の85%が「時間の節約に効果的」とする一方で、「倫理的・感情的な判断は人間が担うべきだ」ということが明らかになりました。今後、AIが中間管理職の業務を担う割合は増えていくと見られますが、多くは人間の監督下での“支援役”にとどまりそうです。
結論として、AIはリーダーを「置き換える」のではなく、「進化させる」存在のようです。
AIをそのまま経営トップに据えるのではなく、人間のリーダーがAIの分析力や実行力を最大限活用する“協働型の経営スタイル”が、これからの主流になっていくようです。人間の直感、共感力、価値判断力、そしてAIの合理性、スピード、スケーラビリティ。それらを組み合わせたハイブリッド経営が、次世代の競争優位を生む鍵になるようです。
※輪番CEOとは、複数の人が交代でCEO(最高経営責任者)の役割を担うシステムです。一定期間(例えば半年、1年など)ごとに、ローテーションでCEOのポストを任せることで、個人の負担を軽減し、組織の活性化を促すという目的があります。